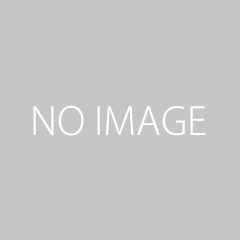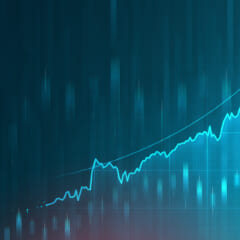システムショック:Storm-0501ランサムウェアがクラウドへ移行

2025年9月17日、Doug Bonderud
全体的にランサムウェアの発生率は低下しています。2025年には、60%強の企業がランサムウェア攻撃を報告しており、実のところ2020年以来の最低の数値となっています。
良くないニュースとしては、攻撃者が戦術を変えていることです。最近のマイクロソフトセキュリティ分析が指摘するように、脅威アクター「Storm-0501」はランサムウェアをオンプレミス環境から移行させ、ハイブリッド環境とクラウド環境の両方を危険に晒しています。以下に詳細を解説します。
How:Storm-0501攻撃の基本(手法)
従来のランサムウェア展開はオンプレミスで行われます。攻撃者はローカルネットワークを侵害し、悪意のあるペイロードを展開します。実行されると、これらのペイロードは重要なファイルを暗号化し、ハッカーは復号鍵と引き換えに身代金を要求します。
最近まで、Storm-0501もこのペイロードの手法に従っていましたが、2024年、この脅威アクターはクラウド環境を侵害可能な新たなマルウェア株を展開しました。攻撃はちょっとした足掛かりから始まります。サイバー攻撃者はActive Directory環境を侵害し、次にMicrosoft Entra IDへ移動します。その後、権限を昇格させて管理者レベルの制御権を獲得します。
これにより、無制限のネットワークアクセスを可能にするフェデレーテッドドメインを追加でき、オンプレミス型ランサムウェアの展開も可能になります。結果として二重の攻撃が成立します。従来のランサムウェアを使用すれば、脅威アクターはオンサイトデータを暗号化し、解放のための支払いを要求できます。一方、完全なクラウドアクセスを活用すれば、保存された資産を流出させ、バックアップを削除し、データを人質に取って身代金を要求できます。
What:侵害の一般的な条件(内容)
Storm-0501の成功の鍵は、オンプレミスとクラウドベースの展開の間の隙間を悪用する二重の侵害手法にあります。
端的に言えば、ハイブリッド環境は純粋なローカル環境に比べて複雑です。企業がクラウドとローカルリソースの両方を最大限活用するには、異なるリソース、サービス、アプリケーションを接続するデジタルブリッジが必要となります。このデジタルグレーゾーンこそが潜在的な問題を生み出します。
MicrosoftによるStorm-0501攻撃の分析を考察しましょう。標的となった企業は複数の子会社を運営しており、各子会社は独立しながらも相互接続されたAzureクラウドテナントを保有していました。各テナントのセキュリティ態勢は異なり、Microsoft Defender for Endpointを導入していたのは1つだけでした。さらにMicrosoftの研究では、複数のActive Directoryドメインが複数のテナントに同期されており、ITチームがこれらのクラウドインスタンスを管理・監視するのを困難にしていたことが判明しました。
攻撃はオンプレミスシステムの複数台への侵入から始まりました。脅威アクターは「sc query sense」や「sc query windefend」などのコマンドでDefender for Endpointの稼働状況を確認。稼働中と判断すると、Evil-WinRMと呼ばれるWindowsリモート管理(WinRM)経由のPowerShellツールを用いて横方向への移動(ラテラルムーブメント)を実行しました。防御が有効でないシステムを特定すると、DCSync攻撃を展開してドメインコントローラーを偽装し、全アクティブユーザーのパスワードハッシュを要求しました。これによりクラウドテナントと保存データのほぼ完全なアクセス権を獲得し、データ窃取と暗号化を可能にしました。
このプロセス完了後、攻撃者は侵害された企業アカウントのTeamsアカウントを利用し、経営陣に連絡して身代金を要求しました。
Where:対策強化が必要な領域
マイクロソフト脅威インテリジェンス部門ディレクター、シェロッド・デグリッポ氏によれば、Storm-0501は重大なリスク要因です。「この脅威アクターは適応力が極めて高く、業種を選ばない標的選定を行う」と同氏は指摘しています。「Storm-0501は戦術を迅速に変更し、幅広い業種を標的とする能力を示しており、クラウドサービスを利用するあらゆる組織が標的となり得ます」
企業にとって、クラウド侵害への移行は、以下の3つの主要領域における強化された保護の必要性を示しています。
検出
企業が潜在的な侵害を早期に検知できればできるほど、問題の排除と影響の修復に備える準備が整います。実際には、標準的なアンチウイルスフレームワークを超え、カスタマイズされた行動ルールや運用条件に基づいて脅威をブロックするエンドポイント検知・対応(EDR)などのソリューションが必要となります。
アクセス
ランサムウェアの種類や標的を問わず、企業は常に最小権限の原則から恩恵を受けます。管理機能へのアクセス権を持つユーザーは少ないほど良いのです。
これは多要素認証(MFA)などのソリューションから始まります。ユーザーが「知っているもの」に加えて「持っているもの」または「その人自身」を提示すること、これを義務付けることで、企業は侵害リスクを低減できます。次に条件付きアクセスポリシーが重要です。単発的な認証ではなく、ユーザーがログインを試みるたびに複数の要素を評価します。例えば、通常のアクセス時間帯外や新規ロケーションからのログイン試行時には、追加の検証を要求することがあります。
これらの利点は理論上だけのものではありません。マイクロソフトの分析によれば、侵害されたハイブリッドテナントにおいて、攻撃者が特権ユーザーとして最初にサインインを試みた際、MFAと条件付きアクセスにより失敗に終わり、ドメインを変更して再試行する必要がありました。
ストレージ
ランサムウェア攻撃の成功は、暗号化、データ窃取、または削除によるストレージの侵害に依存します。その結果、強化されたデータストレージプロセスは攻撃者の試みを阻害するのに役立ちます。一例が、クラウド保存データとデータバックアップ双方のイミュータブルストレージです。イミュータブルストレージの概念は単純です:変更不可能、です。企業は書き込み一回・読み取り多数(WORM)など希望するポリシーを設定でき、データが変更されないことを確信して安心できます。この種のストレージは特にバックアップに有用です。たとえ攻撃者が重要な資産を侵害・削除したとしても、脅威が封じ込められ排除されれば、企業は改ざんされていないデータを復元し再構築できます。
「嵐」を乗り切る
オンプレミスセキュリティが強化されるにつれ、攻撃者は新たな侵入経路としてハイブリッドクラウドを狙っています。多くの企業にとって、クラウド環境のマルチドメイン・マルチテナント特性は、特に子会社ネットワーク間でセキュリティ対策が統一されていない場合、こうした攻撃に対して脆弱性を生み出します。
「嵐」を乗り切るには、検出を優先し、アクセスを制限し、完全なデータ復元経路を提供する三本柱の保護アプローチが不可欠です。