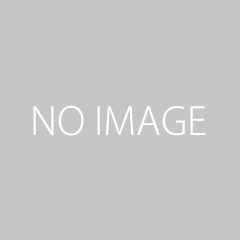生成AIの急速な普及がセキュリティ課題を生む
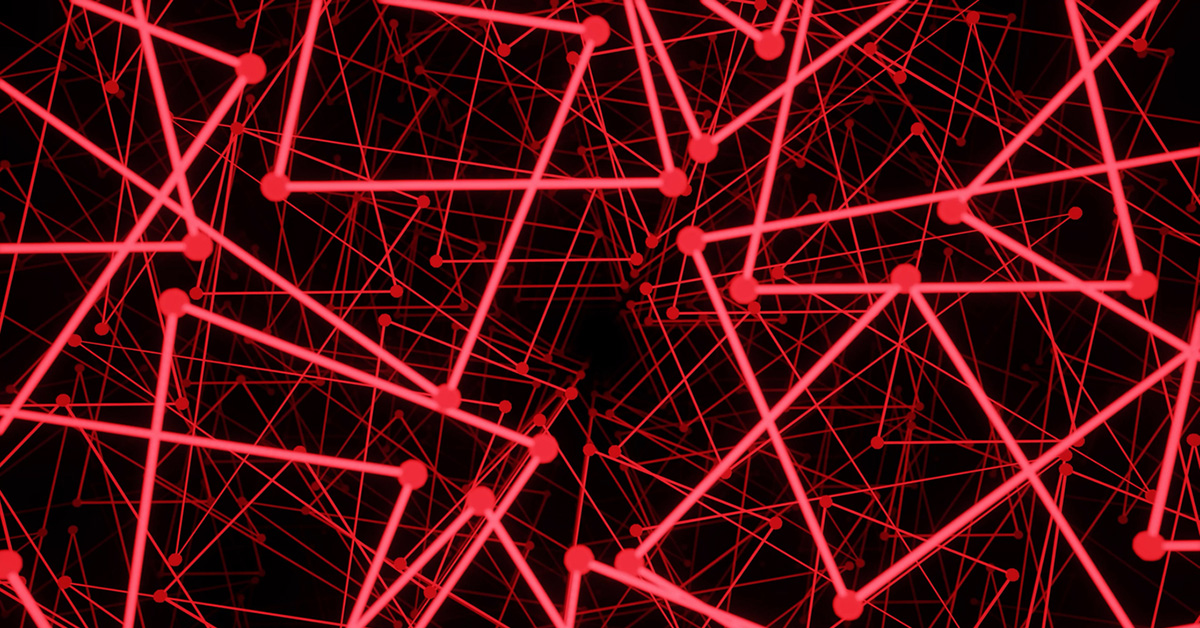
2025年8月5日、Mike Vizard
昨今、サイバーセキュリティチームは、生成型人工知能(生成AI/GenAI)ツールの導入ペースに追いついておらず、特にシャドーAIサービスの利用が増加し続ける中、今後数週間から数ヶ月でデータ侵害インシデントが急増する可能性が高い。
ManageEngineの調査によると、IT意思決定者(ITDM)の70%が組織内で無許可のAI使用を確認しており、従業員の60%が1年前よりも承認されていないAIツールを頻繁に使用している。91%がポリシーを導入しているが、明確で強制力のあるAIガバナンスポリシーを実施し、生成AIツールの無許可使用を積極的に監視しているのはわずか54%である。
また85%が「従業員のAIツール導入速度がIT部門の評価速度を上回っている」と報告。従業員の32%が会社の承認を確認せずに機密クライアントデータをAIツールに入力しており、37%が社内の非公開データを入力した。過半数(53%)が「業務用AIタスクへの個人端末使用が組織のセキュリティ態勢に盲点を生んでいる」と指摘している。
Harmonic Securityの別レポートによれば、生成型ツールへの従業員プロンプトの8.5%に機密企業データが含まれている。入力データのほぼ半数(48%)が顧客データであり、機密従業員データを入力したケースは27%だった。
データ漏洩以外にも対処すべき潜在的なサイバーセキュリティ問題として挙げられるのは、悪意のある出力を生成したり機密データを抽出したりするプロンプトインジェクション攻撃、AIモデル訓練用データの意図的な汚染、AIインフラやAIモデル構築に用いられるソフトウェアサプライチェーンを標的としたサイバー攻撃、そしてAIモデルそのものの盗難である。
現時点で生成AIツールの使用を禁止することは現実的ではないため、多くのサイバーセキュリティチームは、避けられないこれらの侵害を待つのではなく、生成AIの使用状況を積極的に検知・監査・監視する方向へ動いている。こうした知見を武器に、サイバーセキュリティチームが審査した認可済み生成AIツールとワークフローのセットを基盤としたガバナンスポリシーの定義が可能となる。
生成AIツールやプラットフォームの普及に伴い発生するあらゆるインシデントを防止することは不可能かもしれないが、追加トレーニングを少し施すことで、重大な侵害の数を劇的に抑制できると期待される。
もちろん、サイバーセキュリティ専門家が「門が閉まった後で馬を追う」ような状況に陥るのは今回が初めてではない。多くの点で、生成AIツールやプラットフォームの採用は、単に最新のシャドウクラウドコンピューティング事例に過ぎない。唯一の違いは共有される機密データの量であり、これはあまりにも多くの従業員が、例えば数多くのSaaSアプリケーションに関連する過去のクラウドセキュリティインシデントからいまだに教訓を学んでいないことを示唆している。
サイバーセキュリティチームは、生成AI関連のセキュリティインシデントに対処するにあたり、再び、忍耐を要する対応を求められる。しかし同時に、これらは教訓を得られる機会ともいえる。ウィンストン・チャーチルがかつて指摘したように、「良い危機は決して無駄にしてはならない」のであるから。